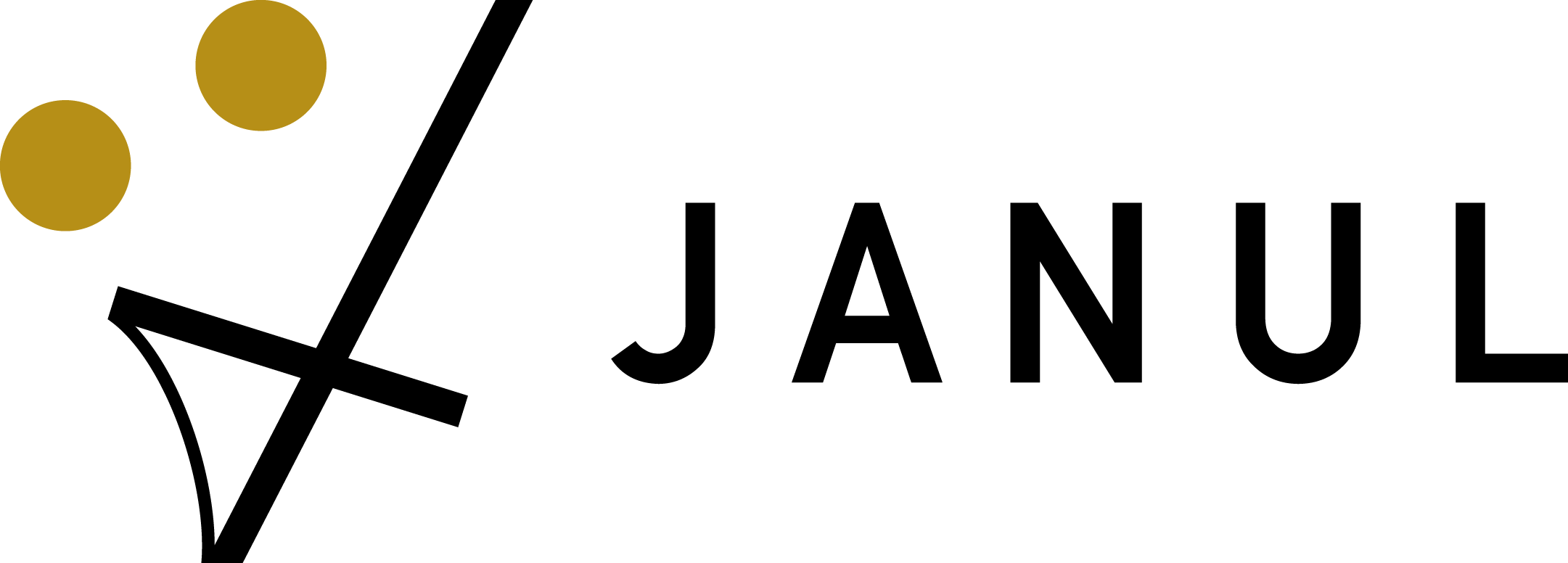浜松医科大学附属図書館の「多様な機能を持った図書館施設」について、浜松医科大学学術情報課目録情報係長(兼)情報サービス係長の柴田佳寿江さんと学術情報課目録情報係の江間利枝さんにお話を伺いました。残念ながら設置当時に担当されていた職員の方が既にいらっしゃらないということで、記録などからお話いただきました。

右:柴田佳寿江さん 左:江間利枝さん ボルダリングウォール前にて
Q.図書館施設にボルダリングウォールや礼拝・授乳施設を設置・併設することになった経緯を教えてください。
柴田: 浜松医科大学附属図書館は令和元年(2019)から令和2年(2020)にかけて改修工事を行いました。これは、図書館と図書館に隣接するエリアを含めた大幅なリニューアルとなっており、スマート・ライブラリ構想(従来型の図書館からSociety5.0*1型図書館へという考えのもと、サイバー空間と実空間を融合させて、融合させたシステムによって諸課題を解決していくといったことを目指す)を立ち上げ、個人学習のためのスペースや、発話学習を行うためのスピーキングルームやスタジオなどが整備されました。また同時に、学内で進められていた国際化推進のための検討も行われました。国際化というキーワードと、隣接エリアがもともと部活やサークル部屋として使用される学生エリアであったことから、学生のための施設として、オープンスペースである松門会(しょうもんかい)ホール(ボルダリングウォールのある図書館玄関ホール)や、礼拝などにも使えるダイバーシティスペース、子どもがいる学生のための授乳室などが作られたと聞いています。ダイバーシティスペースや授乳室は図書館施設ではありませんが、同じエリアにあり、最終的には留学生も含めて学生交流の場として様々な機能を持った場所ができたのではないかと思っています。
*1 内閣府 第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)により提唱された「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」とする概念
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
Q.図書館にはあまり見られない施設ですが、導入にあたって意識した点などあれば教えてください。
柴田: 新たに作られた施設のうち、ダイバーシティスペースや授乳室は国際化推進室(国際化推進センターの事務組織)が、松門会ホールは図書館が管理しています。ボルダリングウォールは図書館の玄関ホールである松門会ホールに設置されています。計画の当初、松門会(浜松医科大学同窓会)の寄付を受けたこのホールに何か象徴的なものを作りたいというところから始まり、いろいろと検討した結果、ボルダリングウォールであれば壁なので邪魔にならないこと、石(ウォールに埋め込まれている登るためのホールド)がカラフルで綺麗なため華やかに見えること、また、医学部の大学ですので、国家試験が近くなると学生が長時間図書館で勉強するという姿があるのですが、勉強の合間に体を動かしてリフレッシュできるという観点から設置されたと聞いています。学内者は24時間図書館利用が可能になっているため、いつでも利用することができます。安全面については、あまり壁を高くせず(設置高2.7m)、でも本気で挑戦しようとするとそれなりに難易度が難しくなるように工夫をしたと聞いています。難易度も易しいものから難しいものまで複数あり、小さなお子さんから大人まで幅広い年代の方々に楽しんでいただけるようになっています。
また、松門会ホールは図書館のゲートの外であるため飲食が可能になっており、昼食や夕食を取ることのできるスペースでもあります。
Q.ボルダリングウォールの実際の利用状況、想定外の利用方法などについて教えてください。
柴田: 自由に使えるため利用状況の記録は取っていないのですが、4月になると新入生が壁に登っている姿をよく見ます。ゴールにベルが設置されているのですが、ベルの音が聞こえてきたら「あ、新入生を迎えたんだな」と実感がわきます。また、印象的な使われ方としては、浜松医科大学のボランティアサークル「四つ葉」が企画した「きょうだいの日:子ども病院探検ツアー」というものがあり、そのツアーに参加する小学生に使わせたいという相談がありました。検討の結果安全面の配慮をお願いした上で了承をしました。学内のイベントで一役買えたというのはとてもうれしい体験でした。
江間: 結構本気でやる方は自分のマイシューズを持ってきて、ボルダリングしている姿も見ました。また、先日は大学の広報誌にボルダリングの写真が掲載されており*2、先生にも利用していただいているんだなと感じました。
柴田: 実現しなかったアイディアレベルでは、新入生のオリエンテーションの一環として福祉体験でアイマスクを付けて構内を歩くという企画があります。そこで、ボルダリングの石のいくつかが、例えばクロワッサンであったり、フランスパンであったり、パンの形をしているものがあるので、そのパンの形を生かして、例えばクロワッサンの石を触ってみようといったミッションを作ってやってみるというアイディアが上がりました。とても面白いことを考えるなと思いました。
図書館でゼミ生を対象に講習会やガイダンスを行った後に、図書館を象徴する場所で写真を撮ろうという先生の呼びかけで、どこがいいかな?やっぱりボルダリングウォールでしょ!と言ってボルダリングウォールの前で、みなさんで写真を撮ったのも印象に残っている出来事です。
*2 浜松医科大学 NEWSLETTER 2024.9(Vol.51 No.1)
https://www.hama-med.ac.jp/about-us/publication/newsletter51-1/#page=13
 |
 |
| パンの形の石:クロワッサン | 中央ピンクがメロンパン |
Q.運用上の問題点や安全確保について教えてください。
柴田: 導入後、事故などは起きていません。壁を高くしないなど、事故を未然に防ぐ対応はしていますし、常設マットも敷いており安全面には気を配っています。先ほどお伝えした「きょうだいの日」で小学生に登ってもらう時は、条件として本学の教職員が必ず安全に配慮して立ち会うこと、小学生にはヘルメット(イベント企画部局にて用意)の着用をお願いしました。
Q.礼拝や授乳のできる施設について教えてください。
柴田: 礼拝などで使っていただけるダイバーシティスペースは、面積としてはそれほど大きくありませんが、よく利用されていると聞いています。図書館に隣接する福利施設棟に設置されており、国際化推進室が管理運営をしています。授乳室の出入り口はこの国際化推進室の中に設置されており、防犯・安全面も配慮されています。
Q.ダイバーシティスペースや授乳室を管理運営している国際化推進室との協力体制はどうでしょうか。
柴田: 図書館と国際化推進室は施設利用の面で協力体制ができており、ボルダリングウォールのある松門会ホールでは国際化推進室のイベントやEnglish Cafeなどを開催しています。また、図書館が管理するワークルームという部屋が福利施設棟の国際化推進室の目の前にあるのですが、そちらで留学生の方の授業やイベントなど、予約してご利用いただくこともあります。施設が一体化しており境目なく使っていただいている印象です。広報の面でも、図書館のサイネージをイベントの案内によく利用していただいています。
Q.今後について教えてください。
柴田: 図書館の特徴ある施設はボルダリングウォールだけでなく、動画の撮影・編集ができる専用スタジオや、発話学習をするためのスピーキングルームなどもあります。学生や教職員に施設の活用方法をお伝えするとともに、国際化推進室と連携を取りながらより良いサポートをしていけたらいいなと思います。
Q.最後に、他大学にボルダリングウォールはおすすめしたいと思いますか?
柴田: スペースを取らず設置できるという面ですごくいい施設だなと個人的には思っていますので、おすすめしたいと思います。
「多様な機能を持った図書館施設」に関する担当窓口および連絡先:
浜松医科大学附属図書館情報サービス係 serv3@hama-med.ac.jp
(@を半角にして送信してください)
--------
※本事例は、募集時に会員館所属職員による「他館の取り組みの推薦」があったものです。
「ビジョン2025重点領域2企画」担当者チーム
岡山大学附属図書館 久磨 由美子(取材・文責)
取材日:2024年12月19日(木)